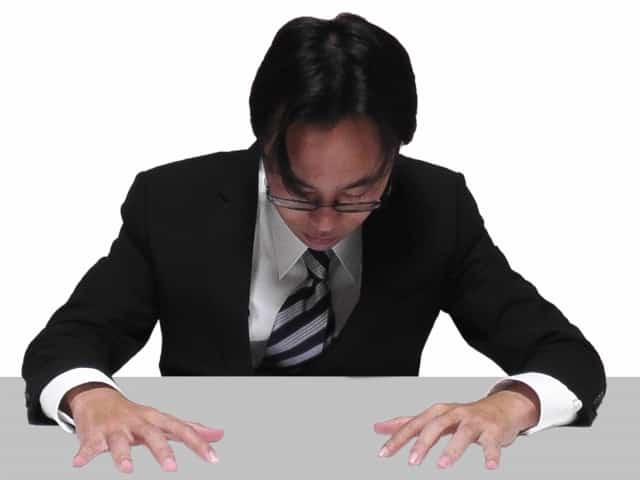「沽券にかかわる」という言葉の意味を知っていますか?
沽券(こけん)とはいったい何なのか・・・ということを知らないと、意味が理解しにくいと思います。
「沽券にかかわる」という言葉の意味や沽券の語源について調べてみました。
どのような時に使うのか、使い方についても解説します。
「沽券」とは?
「沽券にかかわる」という言葉の意味を理解するためには、「沽券」とは何なのか?という点を調べないと始まりません。
「沽券」とは、今の時代で言えば不動産売買契約書のことです。
江戸時代は、土地や家などの不動産の売買は、町役人が立会になって行われていました。
売買の詳細が記載された沽券は、その土地や家の評価を証明するための書類でもあったわけです。
「沽券にかかわる」の意味
「沽券」がどんなものなのかわかると、「沽券にかかわる」という言葉の意味も理解しやすくなりますね。
「沽券にかかわる」とは、
信用を失うこと。
値打ちが下がること。
体面を傷つけること。
面子を失うこと。
このような意味の言葉です。
土地の評価が下がるようなことがあれば、沽券に記載される売買価格に影響があるわけです。
そこから信用を失うようなことを「沽券にかかわる」と言うようになったのです。
「沽券にかかわる」の使い方
「沽券にかかわる」の使い方を例文で見てみましょう。
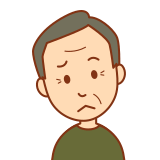
昨日、町内の行事があったみたいじゃないか。
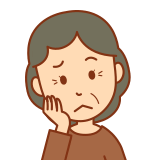
そうなの?
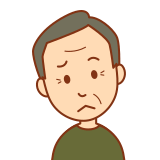
さっきお隣の人から「めずらしく参加しなかったんですね」って言われてはじめて知ったんだ。
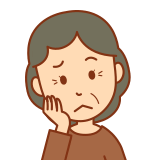
私も知らなかったわよ。
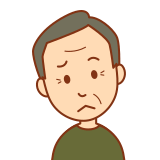
町内の行事の連絡は回覧板で知らせるはずだよ。
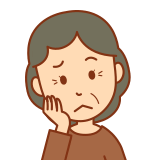
あ・・・。
そう言えば、買い物に出た時に回ってきたからサッと見てお隣に回しちゃったかも。
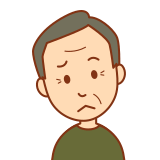
困るじゃないか。
町内会長経験者が不参加じゃ、沽券にかかわるだろう。
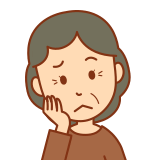
ごめんなさい。
これから気を付けるわ。
このように、その人物の評判が下がるようなことに対して使います。
「沽券にかかわる」の類語
「沽券にかかわる」という言葉の意味から考えると、類義するのは「示しがつかない」とか「立つ瀬がない」があげられます。
「示しがつかない」
「示しがつかない」とは、その人物の評判が下がることでもあります。
とくに目上の者が目下の者に対して「お手本にならない」とか「模範にならない」という時に使います。
たとえば、親が子供の前で失敗してしまう時などに「これでは子供に示しがつかない」などと言います。
お手本になるべき立場の人が、体面を保てない時に使われていますね。
「立つ瀬がない」
「立つ瀬がない」とは、信用を失うことを表しています。
立場がなくなることなので、その場に居られなくなるほど信用を失うことや、世間に顔向けできないような状態になることです。
その場所から追いやられることを「立つ瀬がなくなる」と使う人もいますが、信用を失うようなことに陥っていない時には使わない表現です。
まとめ
現在は、不動産売買を記載する書類を沽券とは呼ばないので、慣用句としての「沽券にかかわる」以外では聞きません。
沽券のことを知らないと、なぜ信用を失うことを「沽券にかかわる」というのか疑問に思ったことがある人もいるのではないでしょうか。
今回の解説が役に立てば幸いです。