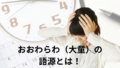「二番煎じ」とは、お茶から生まれた慣用句として知られています。
世の中では、二番煎じはあまり良い意味ではありませんよね。

そうですね
誉め言葉ではないです

悪口とまでいかないけど
言われて嬉しくはないです
というのが一般的な感想ではないでしょうか。
そもそも二番煎じとは、どのようなことを指して使われるようになったのか、その由来や語源、意味について見ていきましょう。
「二番煎じ」の意味
二番煎じとはどういう意味なのか、まずは調べてみましょう。
二番煎じとは一度煎じたものを、もう一度煎じた茶(薬)のこと。
以前の繰り返しで、新味のないものに用いられる。
新明解国語辞典
一般的に用いられている使い方は、この通りですよね。
煎茶は一度目が一番美味しく、二番目は香りも味も落ちることが由来であると考えられています。
語源はどこから
前述のように、二番煎じの意味から考えると、語源は煎茶を飲む習慣が広まってから生まれた言葉だと考えられます。
日本で煎茶が飲まれるようになったのは、意外に歴史が浅く、江戸時代になってからです。
抹茶ではなく、茶葉を煎じて飲むスタイルになったことで生まれた言葉というのが有力な説です。
しかし、異論を唱える人もいます。
というのは、お茶はそもそも中国から日本に伝わったものです。
中国茶の茶葉も日本の抹茶や緑茶の茶葉と同じなのですが、広く飲まれているのは発酵させたお茶です。
中国茶は最初に注いだお湯ではなく、次に注いだ二番煎じがもっとも美味しいとされているからです。
そのことから本来は二番煎じはポジティブな意味だったのに、日本で煎茶が生まれて逆転したのではないかという説もあったのでしょう。
しかし、中国から「二番煎じ」という言葉が伝わったという記録なども見つかっていないそうですし、古くから使われていたわけではないことから、日本で発したと考えるのが自然ではないでしょうか。
二番煎じの例
「昨日から始まったドラマって、去年大ヒットしたドラマの設定に似ているから二番煎じですね」
「あなたの書いた小説は、ベストセラーになった作品の二番煎じじゃないですか!」
「パクリなんて失礼なこと言わなんでください。せめて二番煎じくらいで・・」
「二番煎じだと見抜かれないようにアレンジしないとね」
まとめ
「二番煎じ」はパクりというさらにネガティブな印象の強い言葉に置き換えられて使われることが多くなりました。
なんでも一番が良いと言われる世の中なので、仕方のないことなのかも知れませんね。