ニュースなどで見聞きする言葉には、何となく意味は分かるけど、確かな意味が解らないまま聞き流していることがよくあります。
大人になってからでも、曖昧な理解のままで聞き流していることがあるのではないでしょうか。
更迭という言葉は、ニュースなどでよく聞きますね。
大臣などの立場にある人が、何らかの問題を起こしたりすると、「○○大臣の更迭が決まりました。これは事実上の解任ということでしょう。」なんて言われています。

更迭は事実上の解任、つまりはクビになるってことだよね。

クビにするって言わない理由がわからない

日本語ってめんどくさいよなぁ
こんな感じで何となくの理解のまま聞き流している人も少なくないでしょう。
更迭の正しい意味を知っていると、ニュースの見方も変わるのではないでしょうか。
更迭とは
更迭とは、その地位にある人が変わることを意味しています。
人事異動で立場が変わることが更迭なのです。
事実上の解任という意味で更迭と言われるのは、本来の使い方としては正しくないのです。
ですが、人事異動で肩書が変わる場合は、更迭と言われなくなっています。
更迭を事実上の解任として使う理由
更迭という表現が事実上の解任として使われるようになったのは、スキャンダルや問題発言などで地位のある立場の人を入れ替えることからだと考えられます。
地位のある立場の人が辞めても、その代わりの人がいないと困るので、代わるということで更迭という表現になります。
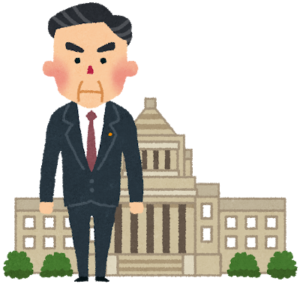
例えば大臣という職務は、内閣総理大臣が任命します。
途中で大臣が交代するのは、何らかの問題があるから入れ替えるわけです。
だから更迭のことを事実上の解任という表現をすることが多くあり、それを見聞きする機会が増えることで、更迭と解任が同じ意味の言葉のように勘違いしてしまうのではないでしょうか。
更迭と間違えやすい表現
更迭は単なる人事交代という意味なので、悪いことをして辞めさせられるとは限りません。
もしも何か問題があって辞めさせられる場合は、解任でもなく罷免という表現が正しいでしょう。
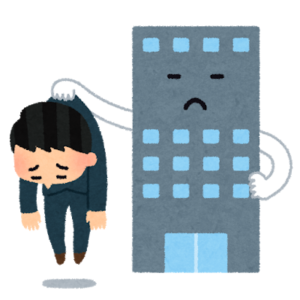
解任はその任務を解くという意味なので、会社であれば役職を解かれて平社員になることも解任となります。
任期が決まっている役職などであれば、任期満了により解任となりますから、解任も悪い意味とは限りません。
問題があって辞めさせられる場合は、免職が正しいのではないでしょうか。
公務員や大臣などの公職をやめさせる場合は罷免です。
まとめ
更迭は事実上の解任とか、何ともまわりくどくてわかりにくい表現をするのはやめて欲しいものです。
マスコミの忖度なのかも知れませんが、正しい表現で伝えてくれないと、勘違いしたまま曖昧な理解をしてしまうので困りますね。



