「おかんむり」とはどんな意味の言葉として使っていますか?
「お父さんがおかんむりだよ」とか「先生は朝からおかんむりで雷が落ちたよ」などと使うことが多いですよね。
「おかんむり」という言葉は、怒っている様子として使われることが多いのですが、なぜ怒っていることを「おかんむり」と言うのでしょう。
当たり前になっているので疑問に思ったこともないという人が多いかも知れませんが、気になった方はチェックしてみてください。
「おかんむり」の語源や使い方など、詳しく解説します。
「おかんむり」の意味
「おかんむり」は、怒っている様子、機嫌が悪い様子を表す言葉です。
ただし、自分が怒っている時や機嫌が悪いことを表すために「私はおかんむりだ」と使うことはまずありません。
「おかんむり」とは、周りの人たちが感じた印象として使う言葉です。
不機嫌そうな様子の人に対して「あの人はおかんむりだ」とか「ずいぶんおかんむりみたいだね」などと使われるのが一般的です。
「おかんむり」の語源とは
「おかんむり」は「お冠」と書くので、この言葉の語源は頭に被る冠が由来になったようです。
「お冠」は「冠を曲げる」という慣用句がもとになっています。
「冠を曲げる」という言葉が生まれた時代ははっきりわかりませんが、冠を頭に被るのは、朝廷に使える公家です。
庶民が頭に冠を乗せることはありません。
ちなみに、武士も正装する時には冠を被ることもありますが、朝廷の使者に会う時など、身分の高い人に会う時などに限らていたようです。

公家が正装するときに被るものが「冠」と呼ばれるものでした。
「冠を曲げる」とは、不機嫌になる様子を表す言葉です。
庶民の間で生まれた言葉だと考えると、かなり痛烈な皮肉がもとになったのではないでしょうか。
「おかんむり」と似ている言葉
「お冠」と同じく、不機嫌になったり、怒っている様子を表す言葉は他にもあります。
へそを曲げる
「へそを曲げる」とは、不機嫌になっている様子を表す言葉としてよく使いますよね。
「いつまでもへそ曲げていないで、みんなと一緒にご飯食べよう」など、不機嫌になったまま、意固地になっている人に対して使うことが多いです。
なぜ不機嫌な様子を「へそを曲げる」と表現するようになったのかと言えば、「へそ曲がり」という言葉がもとになっています。
素直じゃない性格の人を「へそ曲がり」と言います。
不機嫌になって、意固地になっているのは、素直になれないからなので、「へそを曲げる」と言われるようになったのです。
つむじを曲げる
「つむじを曲げる」とは、不機嫌になり、意地悪になる様子を表す言葉です。
つむじとは、頭のてっぺんにあります。
頭髪は渦を巻くように生えているところです。
不機嫌になってそっぽを向くと、つむじの向きが変わるので、不機嫌げ意地悪な様子を「つむじを曲げる」と言います。
「へそ曲がり」と同じく、性格が曲がった人に対して「つむじ曲がり」と言います。
おかんむりの使い方
「おかんむり」の使い方を例文で見てみましょう。
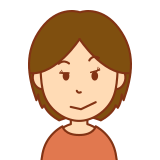
お父さん、連絡もしないで午前様だったでしょ。
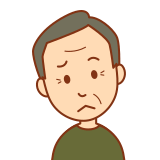
ああ、連絡しようとしたけどバッテリー切れてた。
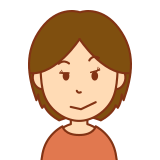
お母さん、今朝もおかんむりよ。
このような会話で使いやすいですよね。
「怒っている」とか「機嫌が悪い」という言葉を使うような時に使います。
関連記事:【くわばらくわばら】はどんな意味?呪文?それともおまじない?
まとめ
「おかんむり」の語源になったのは、公家の被った冠が語源だったのですね。
「冠を曲げる」という言葉は、「へそを曲げる」や「つむじを曲げる」よりも見聞きする機会は少ないですが、「お冠」のもとになった言葉だと考えれば、昔は今よりもよく使われていたのではないでしょうか。



