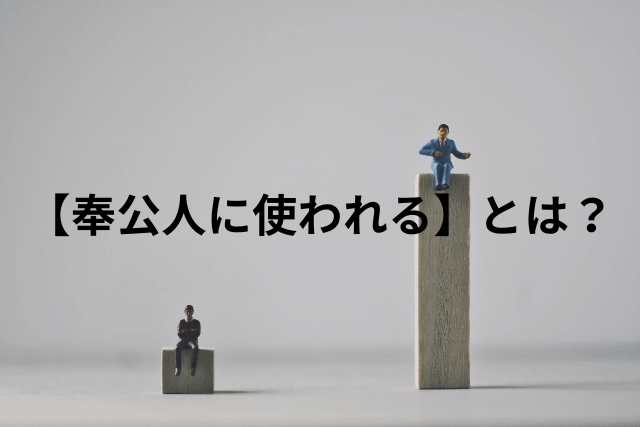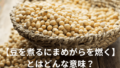「奉公人に使われる」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

う~ん、ありませんね

聞いたことはないけれど、
意味はなんとなくわかります
難しい言葉を使っているわけじゃないので、聞いたことがなかった人でも、意味はきっと理解できると思います。
では、この「奉公人に使われる」という言葉はどのような立場の人がどのような場面で使うのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。
「奉公人に使われる」とは
奉公人とは、現在でいうところの社員、従業員、使用人、スタッフのことです。
もともと奉公とは、国に対して奉仕・奉行することを指していましたが、人物や家に仕えることに変化していきました。
公家や武家に仕えることから、さらに幅広く使われるようになっていったのです。
一般的に主従関係のことをあらわすようになり、商家で働く人のことも奉公人と呼ぶようになっていったのです。
「奉公人に使われる」とは、奉公人を使う側の立場の言葉です。
意味を調べてみると、
奉公人を使うのは、いろいろと気苦労が多く、まるで奉公人に使われているようなものだいうこと。
新明解故事ことわざ辞典
このように書かれています。
同じような意味には「人を使うは使われる」もあります。
人を雇っている立場の人間が使う言葉ですので、人を雇った経験がなければ意味がわかり難いのではないでしょうか。
人を使う気苦労とは
なぜ「奉公人に使われる」という言葉が生まれたのか、それは経営者になってみないとわからないことかも知れません。
商売の規模が大きくなればなるほど、人を上手に使わなければ上手くいきません。
つまり、成功の秘訣は人を使う能力にあるわけです。
人を上手く使うためには、人材が能力を十分に発揮できるように導き、環境を整えることが必要になります。
それが簡単ではないため、人材を育成して能力を発揮させるまでが大変なのでしょう。
また、高い能力を持っている人材が離れてしまうのは大きな損失になるため、待遇面を整えるなど気を使うことも多いわけです。
このように気を使うことが多いので、経営者というのはラクではないという表現として「奉公人に使われる」という言葉が生まれたのではないでしょうか。
「奉公人と牡牛は使いようで動く」とも
「奉公人に使われる」という言葉を発したくなるほど、働く人材の事を考えている経営者もいる反面、ブラックな経営者もいます。
そういう経営者のもとでは、長く働き続ける人も少ないため、結果的には成功も成長も難しいでしょう。
人の口には戸は立てられませんから「あの会社は最悪・・」なんてクチコミが広がれば、求人への応募もなくなるのではないでしょうか。
「奉公人と牡牛は使いようで働く」という言葉は、社員や従業員を牛に並べていて、ひどく見下した意味のように聞こえます。
しかし、機嫌よく働いてもらうための工夫をするのは、人の上に立つ者の能力という意味です。
下手な扱いしかできないと、人も牛も怠けて動きませんから。
まとめ
「奉公人に使われる」という言葉を口にしたくなるほど、人を使うことに神経を使っている経営者は大変でしょうね。
しかし、そういう経営者のもとで働けるのは、幸せですし、頑張って支えようと思えるはず。
結果的には、成功する経営者は気苦労が多いながらも人を使うことが上手なのだと思います。