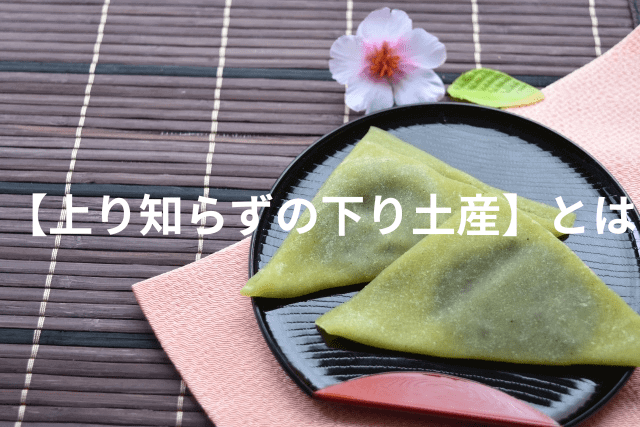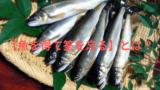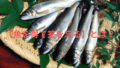「上り知らずの下り土産」という言葉、聞いたことありますか?

私は聞いたことないわ
あなたは知ってる?

いや、ぼくも初耳だよ

なぁ~んだ
ママもパパも知らないんだ

お?知ってるのか?

もちろん、知らない!

・・・・・。
まあ、無理もありません。
今では使う人もほとんどいないので、知らなくても当然と言えば当然かと。
でも、意味を知ると使いたくなる言葉もあるので、せっかくなので調べてみましょう。
「上り知らずの下り土産」とは
「上り知らずの下り土産」という言葉の意味は、
知りもしないのに知っているようなふりをして話すことのたとえ。
新明解故事ことわざ辞典
わかりやすく言えば「知ったかぶり」のことですね。
しかしなぜ「上り知らずの下り土産」というのでしょうか・・。
詳しく調べてみると、なるほどと思う理由がわかりました。
上りと下り
「上り知らずの下り土産」は、知りもしないのに知っているようなふりをして話すことをたとえる言葉です。
この言葉に使われる「上り」と「下り」は、今でも使われる方向、方面のことです。
現在は、東京の向う鉄道や道路は上りと呼びます。
東京を後に進む方面は下りと呼んでいます。
しかし「上り知らずの下り土産」という言葉が生まれたのはいつの時代なのかわかりませんが、上りは京都に向かうことだったのです。
つまり「上り知らずの下り土産」は、京の都に行ったこともないのに、まるで行った経験があるような口ぶりで土産話をすることから、知ったかぶりの様子を例える言葉になったのだと考えられます。
京が都だった時代には、江戸はとても賑やかで栄えていたはずです。
それでもやはり人々は今日の都への強い憧れを持っていたのではないでしょうか。
今でも京都の人たちは、都人としてのプライドを持っていると言われます。
どれほど江戸(東京)が栄えたとしても、やはり雅な京は憧れの地だったのだと思います。
京に行ったことがなくても、まるで行ったことがあるように都の土産話を話すと、きっと人気者になったのではないかと想像できます。
そういう人がたくさんいたので「上り知らずの下り土産」という言葉まで生まれたのではないでしょうか。
「上り知らずの下り土産」の使い方
知ってかぶりをして得意げに話す人に対して、面と向かって使うのではなく、そういう様子をその場にいない人に伝える使い方をします。

まいったよ
部長の話が長くて

もしかして海外留学の自慢話?

あ、それっておなじみなの?

そうよ、みんな聞かされてる

なんだ、そうだったのか
よほど印象深い経験だったんだろうね

いや、ほんとは留学じゃなくて旅行だから!

なんと!!

通り過ぎてもいないニューヨークの話を長々するのよね・・・
「上り知らずの下り土産」とはこのことよ
こんな会話でサラッと使えますね。
まとめ
「上り知らずの下り土産」に通じる意味の言葉には「見ぬ京物語」もあります。
今のように交通手段が発展していない時代には、地方から京都に行くのはとても困難だったはず。
だからこそ、見てきたかのように話しても、嘘だとバレなかったのかも知れません。
知ったかぶりのことをあらわすときに、使ってみてはいかがでしょう。