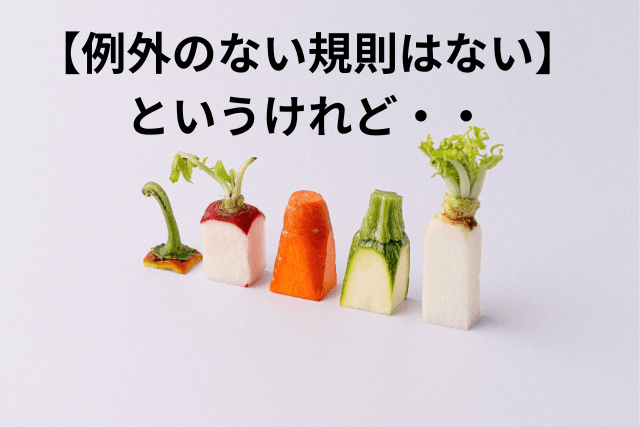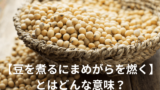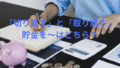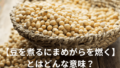「例外のない規則はない」という言葉を知っていますか?
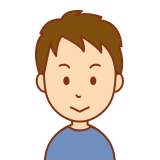
誰かの名言?
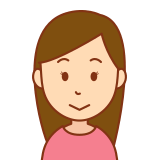
それっぽいね
この言葉は、海外のことわざがもとになっています。
当たり前すぎる意味として理解されるので、あまり使われないのか、それともことわざや格言とは思われていないのかも知れませんね。
「例外のない規則はない」という言葉の意味について、掘り下げてみました。
「例外のない規則はない」とは
「例外のない規則はない」という言葉は、英語のことわざが日本語に訳されています。
There is no generalrule without some exceptions
どんな規則にも、あてはまらない例外が必ずあるものだという意味です。
規則を作るときには、あらゆることを想定して作ったとしても、実際にその規則を運用している間にはあてはまらないケースがあるものですよね。
そういう例外が必ずあるので、規則だけで何もかもが規制できるものではないということなのでしょう。
もともとは、ラテン語の古い諺が広まり、西洋の国々で使われてきた言葉が日本語に訳されました。
「例外のない規則はない」を深堀り
「例外のない規則はない」という西洋で広く使われている言葉には、理屈だけでは物事は進まないので、臨機応変に対応しなければならないという意味でも使われます。
法律や規定、条例に限らず、理屈だけでは解決できない問題もあるので、「柔軟に対応しましょう」という意味でも使われます。
とくに日本では、法律や規則と同じように、理屈や常識、暗黙のルールというような明確ではない決まり事を気にするような印象があります。
法律で禁じられているわけじゃなくても、世の中の常識に外れていることは、非難されて後ろ指をさされても仕方ないと思われます。
つまり、明確な規則のほかにも、守らなければならないルールも山ほどあるので、「例外のない規則はない」という言葉が馴染みにくいのではないでしょうか。
例外が認められないこと
「例外のない規則はない」という言葉に強く反応するのは、もしかしたら大人よりも10代の人たちかも知れません。
なぜなら、校則という規則は、例外を認めないケースが山ほどあるからです。
もともとの髪の色なのに認められずに黒く染めるように強制されたとか・・。
生まれつきの体の特徴だとしても、それが規則に反するとして例外を認めずに無理に規則にはめようとするのは、社会問題にもなっています。
何ごとにも例外があるのだから規則だけでは縛れないということが、なかなか受け入れられない学校が多かったのですよね。
「例外のない規則はない」という言葉が、まったく通用しない環境で成長すれば、このことわざが受け入れられないのもわかるような気がします。
まとめ
格言やことわざは、海外から伝わったものがたくさんあります。
時代はもちろんですが、風土や国民性に合えば広く使われるのでしょう。
「例外のない規則はない」は、あまりに当たり前すぎのですが、それがそうでもないと感じてしまうのは私だけではないと思います。