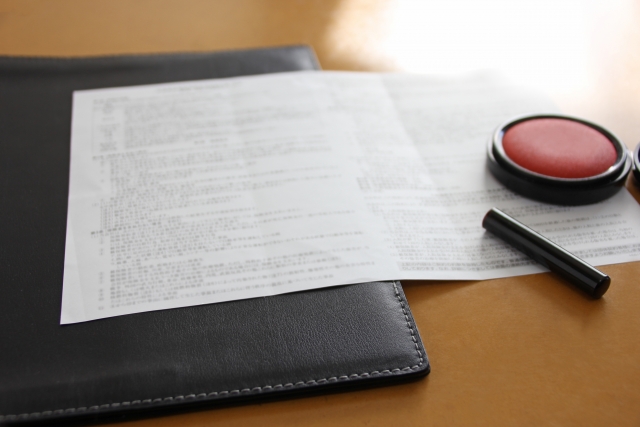小学校の時には算数を勉強していたのに、中学校では数学に変わりますよね。
なぜ算数から数学に変わるのか疑問を持ったことはありませんか?
算数と数学の違いについて調べてみることにしました。
ただちょっと難しくなるだけなのか?と単純に思ってきたのですが、違いがあるのでしょうか。
算数とは

算数は小学校で勉強する「数」の「算術」のことでした。
算術は数の学問の全般として考えるものです。
算数は、現実的な生活で起こることを勉強します。
単純な足し算、引き算、割り算、掛け算、そして速さの計算、時間の計算、割合(%)など、生活する上で知らないと困ることばかりです。
公式さえわかれば、応用して少し複雑な計算もできるようになります。
小学校で勉強する掛け算九九は、小学校で丸暗記します。
小学生の時には、「こんなのおぼえても役に立つのかな」なんて思ったものですが、実際に今でも九九を使って自然に頭の中で掛け算をしていることはあります。
掛け算九九しか暗記しなくなっていますが、足し算九九や引き算九九などもあるようです。
数学とは
中学生になると、途端に算数から数学になります。
算数との違いは、現実に使うこともないし、現実には起こることのない数についても勉強します。

算数は数を使った生活技術なのに対して、数学は数の学問なので知らなくても生活に困らないことも勉強します。
たしかに小学校で勉強した算数は今でも役に立っていますが、中学校で勉強した数学はほとんど覚えていません。
それは日常生活では使うことがないからでしょう。
数学の世界では、今でも新たな計算式を発見すると正解的なニュースになったりします。
算数から数学のなった時点でほぼ置いてけぼりになった私には訳の分からないことですが、数学を知らなくても生きていくことには困らないことだけはハッキリわかりました。
そろばんはどこからきた?

小学校の算数の時間に使うこともあるそろばん。
今では電卓を使うことが多くなったので、そろばんが活躍する場面は少なくなっていますが、珠算教室などは今も健在です。
そろばんはただ数字を打ち込んで計算するだけじゃなく、頭の中での計算も必要なので、数字に強くなると言われて子供のころから習わせると良いと言われています。
日本にそろばんが伝わったのは中国からです。
諸説ありますが、室町時代に伝わったと言われています。
中国では紀元前からそろばんの原型になったものが存在していたというので、すごく古い歴史があるのですね。
そろばんの起源については、中国説が有力ですが、中東の国の説もあり、はっきりした起源はわかっていないようです。
日本では、一気にそろばんが広まり現在でも使われたことから考えると、それ以前は日本の算術の発展はそろばんの普及の効果だったのかも知れませんね。
まとめ
算数と数学の違いはざっくりしたものですが、「生活に必要」か「知らなくても生きられるか」というものだとわかりました。