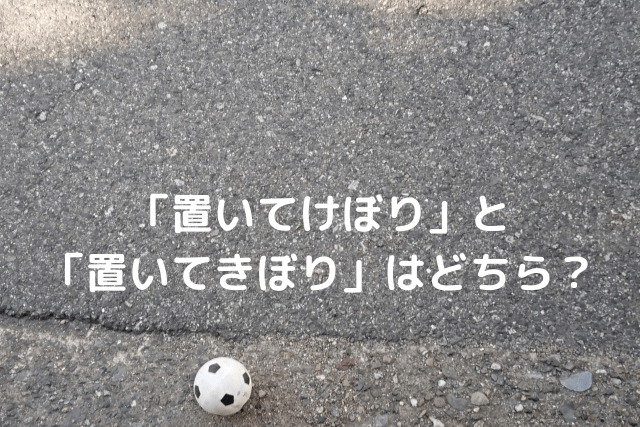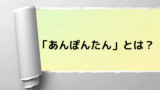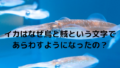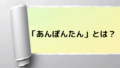「置いてげぼりにしないでよ」と「置いてきぼりにしないでよ」は、どちらが正しいのか知っていますか?
この2通りの言い方は、どちらも同じ意味であることはわかりますよね。
では、どちらが正しいのか、どちらが先だったのか。
また、なぜ「おいけてぼり」「おいてきぼり」になったのか、由来についても掘り下げてみました。
「置いてけぼり」と「置いてきぼり」
「置いてけぼり」と「置いてきぼり」は、現在は「置いてけぼり」の方を使う割合が若干多くなっています。
ということは、先に「置いてきぼり」と言ってったのが「置いてけぼり」に変化したのではないか?と思われるのではないでしょうか。
言葉は変化して、本来のカタチではなくなることが多いですからね。
ですが、今回はそうではありません。
「置いてけぼり」が先にあり、ある時期に「置いてきぼり」を使う人が多くなりました。
しかしまた本来の「置いてけぼり」を使う人が多くなったという珍しいケースです。
つまり「置いてけぼり」が先に生まれた言葉なのです。
「置いてけぼり」の意味
「置いてけぼり」の意味は、置き去りのことです。
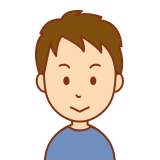
置き去りにされたよ

置いてけぼりにされたよ
同じ意味ですが、「置いてけぼり」の方が軽妙なニュアンスに聞こえますね。
何となく、自然に使い分けている人が多いのではないでしょうか。
置き去りにされたと聞けば、ひどく気の毒な印象になりますから、使い分けが浸透しているのではないでしょうか。
「置いてけぼり」の語源
「置き去り」の意味として使われる「置いてけぼり」の語源は、ある池が由来だと言われています。
江戸時代の怪談「本所七不思議」の中にある「置いてけぼり」が由来だと伝わっています。
この怪談は、落語の演目にもなっています。
江戸の錦糸町堀の付近にあった小さな池で、数人の釣り人が魚を釣っていました。
沢山の魚が釣れて機嫌よく行けを去ろうとしたときに、池から「置いてけ、置いてけ」と繰り返す気味の悪い声が聞こえたのです。
恐ろしくなって池から走り去った釣り人たちですが、家に帰って魚かごの中を見ると、たくさん釣れたはずの魚が消えていました。
それから、気味の悪い「置いてけ」の声はその池で亡くなった人の幽霊だと噂され、いつしかその池は「置いてけ堀」と呼ばれるようになったのです。
まとめ
「置いてけぼり」と「置いてきぼり」は、どちらでも間違いではないのですね。
語源はまさかの怪談話だというのは、落語が好きな人にはわりと知られているとか。
池の呼び名がいつしか意味を持つようになったのは、話のタネにちょうど良かったのではないでしょうか。