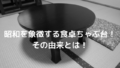「味噌に入れた塩はよそへは行かぬ」という言葉を聞いて、意味がすぐに思い浮かべられる人は、味噌がどのような工程で作られるのか知っているからなのかも知れません。
味噌は大豆と塩と麹菌で作りますから、塩は欠かせない材料ですからね。
ですが「味噌に入れた塩はよそへは行かぬ」という言葉は、味噌作りをたとえて伝えようとしていることがあるはずです。
何を伝えるために、味噌作りをたとえに使ったのでしょうか。
その意味や使い方を見ていきましょう。
「味噌に入れた塩はよそへは行かぬ」とは
「味噌に入れた塩はよそへは行かぬ」とは、
他人のために尽くしたことは、そのときは無駄なように思えても、やがて自分のためになる。
新明解故事ことわざ辞典
という意味なのです。
味噌を作るときには欠かせない塩ですが、味噌の中に入れてしまえば塩は見分けがつかなくなりますよね。
塩の存在は目に見えなくなりますが、塩がなければ味噌の味は完成しません。
塩は味噌の中に入っても消えてしまうわけではないのです。
「味噌に入れた塩はよそへは行かぬ」の使い方
どんな場面で使うのか、例文で見ていきましょう。
例文①

どうしていつも僕ばかり急な残業を頼まれるんだろう

断られないと思っているからじゃない?

NOと言わない僕が悪いのか・・

そんなに落ち込まなくても・・。
「味噌に入れた塩はよそへは行かぬ」って言うでしょ!

何ですか?それは

無駄なことしているように感じても、
いつか自分のためになるってこと

へえ、いい言葉ですね
例文②
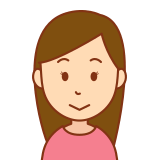
年金って、メチャメチャ高いけど、
私たちが高齢者になったらもらえるのかな
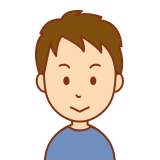
疑問に思うことはあるよね。
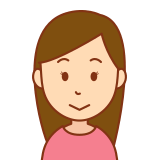
自分で貯金した方がマシのような気もするよ
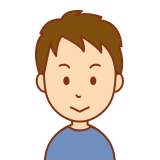
わかるけど、自分のためでもあるんだよ
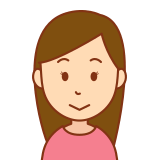
そうなのかな
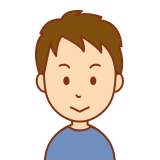
もし年金も健康保険制度もなくて、
全て自分の責任になると大変だよ。
子供や孫の負担はすごいことになる。
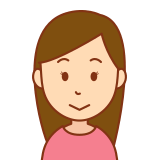
そうだね、1人で親や祖父母を支えるとなれば、
年金とは比較にならないほどの重い負担だ
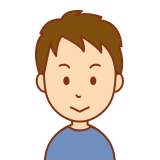
「味噌に入れた塩はよそへは行かぬ」といって、
意味のないことに感じても、自分のためになると思えば、
気分も違うでしょ。
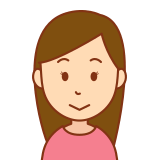
なるほどね
「味噌に入れた塩はよそへは行かぬ」の類語
人のためにしていることのようでも、結果的にはまわりまわって自分のためになるという意味では、
「情けは人のためならず」ですね。
この言葉は勘違いされやすいのですが、人に情けをかけるのは甘やかすので良くないというような意味ではないことは、最近は広く知られるようになりました。
人へやさしくしていると、そのやさしさはまわりまわって、いつか自分へ返ってくるという意味なので、「味噌に入れた塩はよそへは行かぬ」と通じています。
人にやさしくすることで、甘えてしまい、結果的にその人のためにならないという意味であれば、「情けが仇」「慈悲が仇」というのが正しい使い方です。
まとめ
「味噌に入れた塩はよそへは行かぬ」の意味には、表面的には目立たないけれど、欠かせない大切な存在のことを表すのにもピッタリだと思います。
塩味のしない味噌なんて、ちょっと想像できませんものね。
自分のしていることが無駄なことのように感じたときには、思い出したい言葉ではないでしょうか。