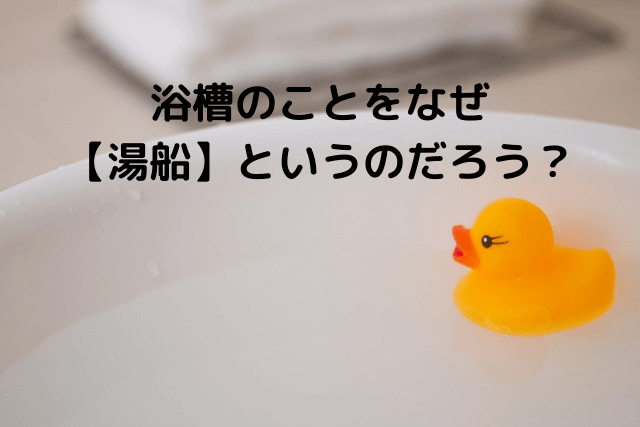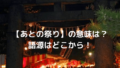お風呂にお湯を溜めるときに「湯船にお湯を張る」という表現をすることがあります。
なぜ浴槽のことを湯船と呼ぶのか、不思議に思ったことはないでしょうか。
浴槽のことを湯船と呼ぶのには、どんな由来があるのか疑問が湧いたので調べてみました。
水に浮かぶ船とは何か関係があるのでしょうか。
浴槽を湯船と呼ぶ理由
浴槽、バスタブ、風呂桶など、呼び方は色々あります。
湯船(湯舟)もその一つです。
あまりにも当たり前に使っている湯船という呼び方ですが、なぜ船が使われているのでしょう。
湯船の語源を調べてみると、お風呂の歴史をさかのぼることになりました。
今の時代、家にお風呂があるのが当たり前ですが、昔はそうではありませんでした。
田舎の家には風呂が各家庭にあったとしても、江戸のような人口の多い都市部では長屋が多かったのです。
長屋にお風呂はないので、江戸の庶民は銭湯を使っていました。
それは地方の都市部でも同じだったようです。
じつは湯船の語源は、銭湯だったのですよ。
家にお風呂がない人たちのために、料金を取ってお風呂を提供する商売が生まれた当初は、固定の場所ではなく移動銭湯から始まったのです。
お湯を入れた浴槽を移動させるのはかなりの重労働です。
だから船にお湯を張った浴槽を乗せて、港や川に停泊していたのです。
まさに湯の船が移動していたので、湯船と呼ばれるようになり、それが現在の【湯船】の語源になったのです。
お風呂の入り方の変化
船にお湯を張った浴槽を乗せて移動する銭湯が流行り始めたのは、江戸時代の中期から後期だと言われています。
船タイプの銭湯は、浴槽にたっぷりとお湯を張っているのが特徴でした。
それが人気となってから、お湯をたっぷりと入れた風呂が当たり前になっていきました。
じつは江戸時代中期までの銭湯は、蒸し風呂が主流でした。
現代で言えばサウナ的な風呂です。
しかし移動式銭湯のように、たっぷりとお湯を張った方が人気を集めるようになったため、陸地の銭湯もお湯をたっぷり入れた風呂に変化していったのでしょう。
移動式銭湯の湯船から、銭湯のスタイルが変化して、それが現在にも残ったので、湯船という呼び方も残ったというわけです。
風呂桶は家風呂の主流だった
浴槽のことを湯船という他に風呂桶と呼んでいたのは、本当に桶を作る職人が浴槽を作っていたからです。
個人の家の浴槽は、五右衛門風呂から木製の桶に変化していきます。
昭和初期までは、家風呂はまだ普及率がそれほど高くなかったので、木製の風呂桶が主流でした。
しかし戦後の高度経済成長期になると、各家庭に浴室が設置されるようになり、急激に浴槽の需給が高まります。
そのころから、西洋タイプのバスタブが日本の家風呂の主流にとってかわったのでしょう。
まとめ
湯船という呼び方は、何となくお湯に入ってゆらゆらと船のように浮かぶ様子が語源だと想像していました。
まさかホントにお風呂を船に乗せて移動させる銭湯があったとは!
江戸時代の銭湯文化って、謎が多すぎて面白いです。