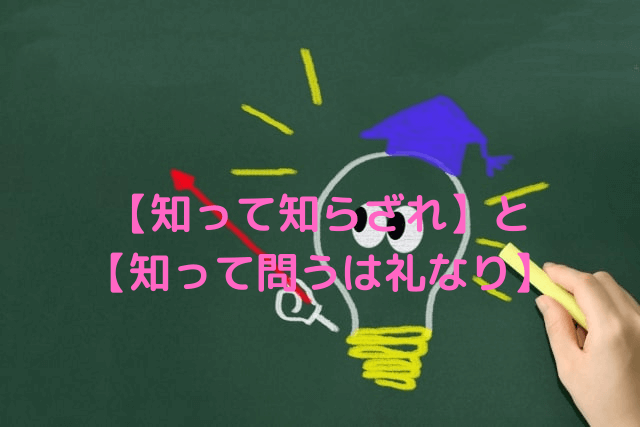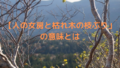「知って知らざれ」と「知って問うは礼なり」は、どちらも「知る」ことに関わる言葉のように思います。
「知る」ことについて、どんなことを伝えようとしているのでしょうか。
2つの言葉はまったく別の意味があるのか、それとも何か共通する点があるのか疑問に思ったので、それぞれの意味について詳しく調べてみました。
「知って知らざれ」の意味
「知って知らざれ」とは、
たとえよく知っていることでも、それをひけらかさないことが、奥ゆかしい態度である。
という教えの意味があります。
大抵の人は、自分がよく知っていることであれば、得意げになって「これはね~」と自慢するように話したくなるものです。
ですが、そういう態度をするよりも、よく知っていることでもひけらかさない方が良い印象を与えます。
そういう奥ゆかしさが大切だという教えを伝える言葉なのです。
「知って知らざれ」の類語
「知って知らざれ」と似ている意味の言葉に
「能ある鷹は爪を隠す」があります。
よく使われるので、知っている人が多いのではないでしょうか。
他にも「知って知らぬ顔が真の物知り」という言葉もあります。
「知って知らざれ」とほぼ同じ意味です。
本当に物知りで知識の豊かな人ほど、人前では知らないような顔をしているということです。
真の物知りがいるのに、自慢して知っていることをひけらかすのは、とても恥ずかしいですよね。
知識をひけらかしたくなった時には、周りに真の物知りがいるかも知れない・・と思って、控えめにした方が良いのでしょう。
「知って問うは礼なり」の意味
「知って問うは礼なり」という言葉には、「知って知らざれ」とは無関係とは思えない意味があります。
「知って問うは礼なり」とは、
知っていることでも、ひとつひとつたずねて、慎重に行うのが礼儀である。
という意味があります。
知っていることなのに、わざわざ人に尋ねることが礼儀というのは、少し不可解です。
しかし、知っているつもりでも、それが正しいとは限りません。
そういう慎重な態度こそ、礼儀だという教えなのです。
「知って問うは礼なり」の語源
「知って問うは礼なり」という言葉は、孔子の言葉がもとになっています。
それは、孔子が役人になり、初めて君主のところに行ったときのことです。
そのとき孔子は、儀礼について係の人に1つずつ尋ねたのです。
孔子は礼の学者として知られた人物だったのに、「そんなことも知らないのか」というような言葉を言われてしまいます。
それに対する孔子の言葉が「知って問うは礼なり」の語源なのです。
1つ1つ尋ねることで、無礼を防ぐことができるので、結果的にはその慎重さが礼儀だということなのでしょう。
まとめ
知識を深めると、つい言いたくなるのは自然なことだと思います。
せっかく身につけた知識なので、それを披露する場面があればアピールしたくなるものでしょう。
ですが、「知って知らざれ」という言葉を思い出すと、ひけらかすような態度にならないように気を付けられると思います。
また「知って問うは礼なり」のように、知っていることで気が大きくなることなく、慎重になることも礼儀として頭の片隅に置いておきたい言葉ではないでしょうか。