筍といえば、成長がとても速くて、土の中からほんの少し頭が出ている状態で掘り起こさないとすぐに伸びて食べられない状態になります。
竹になるまでには少し時間はかかるとしても、食べられる筍の状態はほんの短い期間なのです。
破竹の勢いなんて言うことわざにもあるように、とにかくグングンと成長が早いのが筍の特徴です。
では、縁の下の筍とはどんな意味なのでしょう。

聞いたことある?
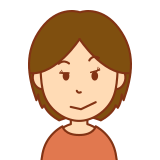
初耳かも・・・

私も(笑)
成長の早い筍を使ったことわざなので、縁起の良い意味なのでしょうか。
縁の下の筍とは
縁の下の筍の意味は、上に伸びようとしても頭が使えてしまうので伸びることができないことを表現しています。

ということで、縁の下の筍ということわざは、いわゆる「うだつの上がらない人」のことを例えているのです。
うだつの上がらないとは、出世できない、大成しないという意味です。
どれほど筍が勢い良く伸びようとしても、縁の下に生えてきては頭がつっかえてしまうので、それ以上は伸びることができませんから、このようなことわざになったのでしょう。
縁の下の筍の意味を深読みする
縁の下の筍の意味は、ただうだつの上がらないこととで終わらせてしまうのは、いささか違和感を持ちました。
筍の成長を邪魔するのは縁の下です。
縁の下にさえ生えてこなければ、立派に成長することができたのに・・。
深読みし過ぎかも知れませんが、せっかく伸びようとしている人の頭を押さえつける邪魔者がいることを想像してしまいました。
ただ自分の怠慢で出世できないのではなく、頭を押さえつけて邪魔されてしまった人のことだと感じましたが、皆さんはどう思われたでしょう。
縁の下の筍に似ていることわざ
縁の下を舞台にしたことわざといえば、縁の下の力持ちが有名です。
しかし、縁の下の筍とは全く違う意味ですよね。
見えないところで支えることで、とても良い意味のことわざです。
縁の下の筍に似ていることわざに、縁の下の鍬使いというのがあります。
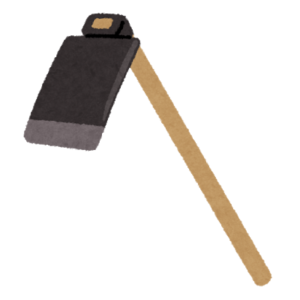
鍬(くわ)は農作業で使う道具ですが、縁の下では窮屈で使えません。
縁の下の鍬使いとは、思うように力を発揮することができないとか、自由を制限されている状態で働くことの不自由さを表現することわざです。
縁の下の筍とは少し共通するところがあります。
どちらも頭を押さえつけられて窮屈だから、本来の姿になれないわけです。
想像すると、縁の下の鍬使いは無理難題ですよね。
まとめ
縁の下の筍ということわざの意味を知った時、家庭の事情で勉強する環境を失ってしまう子供たちを思い出しました。
縁の下の筍になる子供たちが一人でも減るような社会になって欲しいものです。


