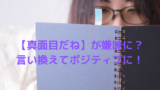社会人になって、初めて自分の名刺を持った人も多いのではないでしょうか。
名刺はビジネスには欠かせないツールです。
新入社員は、まず名刺交換の練習から始めるという企業もありますよね。
その名刺ですが、当たり前に「名刺」と読んでいますが、なぜ「名紙」じゃないのか不思議に思いませんか?
名刺は、ほとんどが紙製です。
それなのになぜ名前を刺すなんて文字になったのでしょうか。
名刺の語源や歴史について調べてみました。
名刺の語源
名刺は紙製で作られているものがほとんどなのに、なぜ名紙ではなく名刺なのか・・。
その理由を知るためには、名刺の語源をさかのぼる必要があります。
名刺は、中国で生まれたものです。
唐の時代に竹を削ったものに、名前を書いたものが名刺の始まりだと言われています。
なぜ竹を削ったものに名前を書いたのか・・というのは、諸説あります。
有力な説は、訪問先が留守だったときに、「○○が訪ねた」ということを残すために竹を削り、名前を書いて玄関先に置いたことが始まりという説です。
刺という字は、トゲとも読みます。
つまり、竹を細く削った木を刺と呼んでいたことが、名刺の語源になったというわけです。
現在の名刺はほぼ紙製ですから、刺という字が使われることに疑問を感じる人もいるでしょうが、語源を知ると理解できますね。
名刺の歴史
中国で生まれた文化が日本に伝わり、今の時代まで根付いているものは数えきれないほどあります。
ビジネスシーンで欠かせないツールとなっている名刺も、中国から伝わった文化です。
日本で名刺を使うようになったのは、江戸時代からです。
中国と同じように、訪問先が留守だったときに、名前を書いて不在時に訪ねたことを知らせるために置いておくための目的でした。
ただ、日本は和紙を作る技術が高く、江戸時代には和紙が様々な用途で使われていました。
名刺も和紙に名前を墨で書いたものでした。
その後、武士たちが自分の紋を名前と一緒に記して印刷するものも使われるようになったので、今のビジネスシーンでのツールの使い方の基礎は江戸時代にはすでにあったのです。
世界の名刺文化
日本でも、趣味の交流のために名刺を作る人も増えていますが、やはり名刺はビジネスツールの印象が強いですよね。
しかし海外では、日本のような名刺交換の風景は珍しいのです。
ヨーロッパでは、18世紀のころに社交界で名刺を作るのがブームになったそうです。
アメリカでも、社交の目的で資産家が名刺を作ったようですが、西洋文化では自分の存在を宣伝するためのツールというのが主流だったようです。
まとめ
名刺がなせ名紙ではないのか・・という疑問は解決しました。
名刺は、初対面の人に自分の名前をおぼえてもらうためには、とても便利なツールです。
それはシャイな人が多い国民性には、ピッタリだったのかも知れませんね。