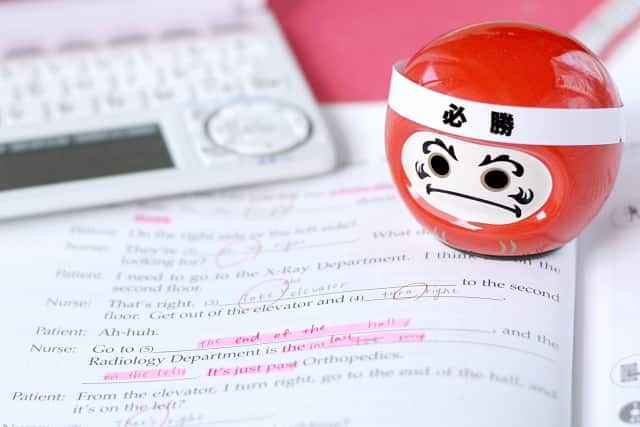テスト前の勉強の方法として「ヤマをかける」とか「ヤマをはる」ということがありますよね。
そのテストの結果が良かったりすると、「ヤマが当たった」となり、結果が悪ければ「ヤマが外れた」となります。
当たり前に使われているのですが、「ヤマ」の語源とはどこから来たのでしょう。
「ヤマをかける」の「ヤマ」の由来について解説します。
「ヤマをかける」の意味とは
「ヤマをかける」とは、もしかしたら?の可能性に期待して、予想をするという意味です。
テストの時などに「ヤマをかける」とか「ヤマをはる」と使われるのは、テスト範囲の中から、出題されそうな箇所を予想して、その部分を重点的に勉強する方法のことを表現しています。
広い範囲の勉強を浅くするよりも、ポイントを絞って重点的に勉強した方が、予想が当たった時には良い結果になります。
ですが、その予想が外れてしまった場合は、ひどい結果になります。
「ヤマをかける」とは、あてずっぽうに予想するという意味でもあるため、テストの勉強法としては、あまり褒められることではないですよね。
「ヤマをかける」の語源
「ヤマをかける」や「ヤマをはる」の「ヤマ」の語源は、「山」です。
ただ、山は山でも鉱山のことです。
鉱山とは、石炭、銀、金、銅などの鉱物が採取できる山のことです。
金属製の鉱物と、石炭などの燃焼資源になる鉱物が採取できる山など分類されますが、広く鉱山と呼んでいます。
あてずっぽうに予想して可能性を期待するという意味で「山をかける」と言われるのは、鉱山を見つける山師が使っていた職業用語が語源でした。
山師とは、どの山に資源となる鉱物があるのか探し当てる人です。
しかし、表面だけ掘っても見つけられないので、予想してかなり深く掘り進めても鉱物が見つけられないことも多かったのです。
つまり、かなり投機性の高い予想が「山をかける」という意味なのです。
外れてしまえば大きな損失になるし、当たれば大きな利益になります。
ハイリスクハイリターンを意味する慣用句として、「ヤマをかける」や「ヤマをはる」という表現が一般の人たちにも広まっていったのでしょう。
「ヤマをかける」の類義語
「ヤマをかける」と同じように、ハイリスクハイリターン意味として使われている表現を集めてみました。
「神頼み」
「出たとこ勝負」
「イチはバチか」
「運任せ」
「リスキー」
「のるかそるか」
このように、同じような意味の言葉をいくつか見ると、「ヤマをかける」ことがいかに地道な努力からかけ離れているのかよくわかりますね。
まとめ
「ヤマが当たった」とテストの結果を見て喜んでいる人は、次もヤマをかけようとするでしょうね。
でも、そんなにイイことばかり続きませんよ。
テストの時に焦らなくて済むように、日々の積み重ねが大切ではないでしょうか。
[https://kotobanogimon.life/?p=454]