「学者貧乏」という言葉を聞いたことがありますか?
学者というのは、学問に通じて、学問を職業としている人のことです。
日本人の学者がノーベル賞を受賞すると、ニュースなどで大々的に取り上げられますね。
多くの学者は、研究のために大学や企業の研究室に所属しているようなので、貧乏というわけではなさそうです・・。
なぜ「学者貧乏」という言葉があるのか、その意味や使い方、類義語などをご紹介しましょう。
「学者貧乏」の意味とは
「学者貧乏」とは、
学者は学問には通じているが、お金を稼ぐことや儲けることは不得意な人が多い。
故に、学者の実生活は貧しいものだ。
という意味があります。
冒頭にも書きましたが、現代の学者は研究者と呼ばれる人が多く、大学や企業の研究室に属して専門の研究をするので、お金に苦労しているイメージはありません。
ですが、研究には莫大な資金が必要なので、支援するスポンサーなどが見つけられないと、研究を続けられないこともあるそうです。
とくに日本は研究のために国がお金を出し渋る傾向があるらしく、有能な学者はアメリカなどの海外へ渡ってしまうことが多いのです。
ips細胞の研究でノーベル賞を受賞した山中伸弥教授は、研究者でありながらも資金を集める能力にも長けていると言われているので、全ての学者に「学者貧乏」が当てはまるわけではないでしょう。
ですが、昔は学問のために自分の家の財産を投じる学者も沢山いたので、「学者貧乏」という言葉がリアルに当てはまる人が多かったのでしょう。
「学者貧乏」の使い方
「学者貧乏」の使い方を例文で見てみましょう。
例文①
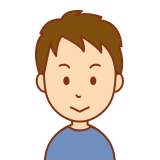
大学院まで行ったのに、いい就職先が見つからなかったらしい。
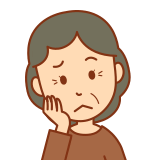
勉強ばかりしていたから、面接とか苦手なんじゃないかしら。
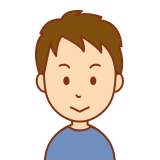
周りから学者貧乏をリアルに再現してるって言われてるらしい
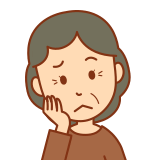
大学院で研究してたことも生かせずに、アルバイトしかできないなんて、勿体ないわね。
例文②
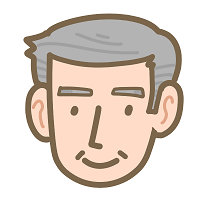
君のお父さんはたしか○○大学の教授だったな。

はい。
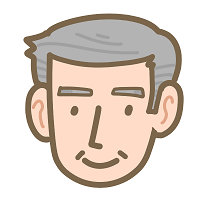
君はお父さんと同じ研究者の道には興味なかったのかい?

はい。
研究者の家族は大変なんですよ。
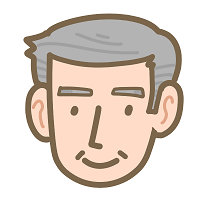
なるほど、そうかもしれないな。

学者貧乏がそのまま我が家に当てはまる言葉で、母親はかなり苦労してました。
「学者貧乏」の類義語
「学者貧乏」と似た意味の言葉は、ほかにもいくつかあります。
類義する言葉を集めてみました。
学者と役者は貧乏
「学者と役者は貧乏」は、どちらもお金に縁が薄い職業ということです。
学者は研究に没頭するためお金を儲ける欲がなく、役者は人気を得るためにお金を派手に使うので、身につくお金がないと思われたからでしょう。
軍者ひだるし儒者寒し
「軍者ひだるし儒者寒し」は、どちらも立派なことを言うわりに、実生活は貧しいという皮肉から生まれた言葉です。
軍者とは、戦い方を教える兵法を説く人のことです。
儒者とは、儒学を説く学者のことです。
どちらも尊敬される人物のはずですが、その日の暮らしを生きることに精一杯の人にとって、学問は二の次だったのでしょう。
立派なことを説いているのに貧しいのなら、まず豊な暮らしをするための方法を学んだ方が良いと思って皮肉を込めて生まれた言葉だと言われています。
寺子屋に家持ち無し
「寺子屋に家持ち無し」とは、寺子屋で庶民の子供に学問を教えている人物も、寺子屋で学問を教えてもらう子供の親も、立派な家を持っている人はまずいないという意味です。
寺子屋とは、江戸時代に生まれた庶民の子供のための学習塾のようなものです。
学問は大切だとわかっていても、働いてお金を稼ぐ方が重要だという批判的な意味が込められています。
肥えたる仙人富める道士あることなし
「肥えたる仙人富める道士あることなし」とは、霞を食べて生きていると言われる仙人や、道教を伝えることを仕事とする道士をたとえとしています。
仙人が太っていたり、道士が裕福な暮らしをすることはあり得ないことを表しています。
学者と色男に富めるは少なし
「学者と色男に富めるは少なし」とは、学問に通じている学者と、女性にモテる色男はかけ離れているのに、どちらも裕福な人は少ないという意味です。
学者がお金儲けが苦手なように、色男も働くのが苦手なタイプが多いからでしょう。
まとめ
「学者貧乏」という言葉は、今の時代の学者さんを見ていると、あまりピンとこないかも知れません。
ですが、研究に没頭していると、お金のことなんて考えられなくなるのもわかるような気がしますよね。



