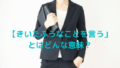「どこのカラスも黒い」とは、黒い羽をもつ烏を用いた慣用句です。
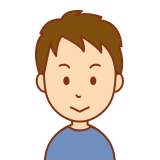
カラスが黒いのは
当たり前のことだよね
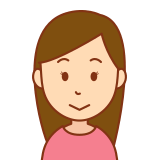
それをあえて使うのだから
きっと深い意味があるのでは?
そうなんですよね。
ごく当たり前のことを、何のひねりもなく「どこのカラスも黒い」というだけなら、慣用句として成り立たないでしょう。
じつはこの言葉には、2通りの意味があると言われています。
どんな意味があるのか、詳しく調べてみました。
「どこのカラスも黒い」とは
「どこの烏(カラス)も黒い」の意味です。
2つの意味の例えとして使われます。
1つ目は、どこへ行っても、さほど目新しいこともなければ変わったこともないというたとえ。
カラスの種類は日本に生息しているだけでも7種類もいます。
世界中のカラスの種類はその何倍、何十倍にもなるわけですが、どこへ行ってもカラスは黒い羽を持っており、それはどこでも同じです。
遠い土地へ行けば、さぞかし目新しいことがあるのではないかとワクワクするでしょうが、さほど変わらないものだということのたとえとして「どこのカラスも黒い」と言うのです。
2つ目は、人間の本性というのは、どの国で生まれて育ったとしてもたいして違わないことのたとえ。
生まれた国が違えば、生活習慣、価値観や文化も違うとしても、人間の本性は生まれた国が違ったとしても大差ないという意味で使われることもあります。
「どこのカラスも黒い」の類語
「どこのカラスも黒い」という慣用句と同じ意味の類語には、「どこのニワトリも裸足」という言葉があります。
どこに行っても鶏は裸足だというのは、当たり前ですが、他の鳥に裸足じゃないのがいるのか?と不思議に思います。
あえて鶏を使ったのは、人間が古くから育ててきた種の鳥だからではないかと推察します。
「どこのカラスも黒い」の対義語
「どこのカラスも黒い」という慣用句に対義するのが「ところ変われば品代わる」です。
「ところ変われば品変わる」の意味を調べてみました。
その土地土地により、風俗・習慣・言語などが違う。また同じものでも土地が変わると名称も用途も変わるということ。
新明解国語
例えば、関西と関東では、桜餅と呼ばれる和菓子もまったく別物です。
逆に同じものでも土地が変われば名称の違うものもあります。
「難波の葦(あし)は伊勢の浜萩(はまはぎ)」
「品川海苔は伊豆の磯餅」
また、「ところ変われば水変わる」という言葉もあります。
水質はその土地の地層の違いで水質も違うことから、他の土地へ移り住むと水の違いでお腹の調子を壊すことがあることが由来の言葉です。
生きる上で欠かせない水をたとえにして、他の土地では文化や習慣に違いがあることを忠告する意味が含まれているのでしょう。
まとめ
「どこのカラスも黒い」という言葉について解説しました。
最後に余談ですが、カラスなのに白い羽の個体も存在します。
そういう種ではなく、色素異常によるもので、数万羽のうち一羽生まれるかどうかの希少な白いカラスです。
目立ってしまうため、外敵に狙われやすくなるということから群に入れないなど、生き抜くのが難しいこともあるそうです。
神々しい姿から、神の化身と呼ばれることもあるそうなのですよ。