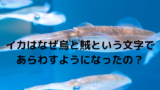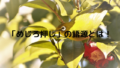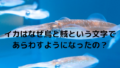「気の毒」という言葉は、何となく「可哀想」とか「同情するわ」みたいな意味で使われていますよね。
それが当たり前になっているので、とくに疑問にも思わなかったのです。
しかし、ふと考えると何だか疑問が・・
なぜ「気の毒」という表現が同情をあらわす言葉になったのか。
その語源や意味、使い方の変化などに注目してみました。
「気の毒」の意味とは
「気の毒」の意味を調べてみました。
1、他人の境地を見聞きして、心から同情に堪えない気持ちを示す
2、他人の余計な心配をかけて、悪かったと思うこと
新明解国語辞典
このような意味は、私たちが普段から使っていることと同じです。
使い方としては、間違っているわけではないのですよね。
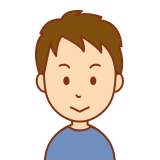
約束をすっかり忘れて、すっぽかしてしまって気の毒なことをしたよ

ひとりで残業を押し付けられて、ほんとに気の毒でしかたない
このような使い方のほかにも、
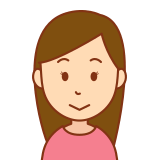
タッチの差で間に合わなかったのね、お気の毒さま

気の毒だと思うけど、世の中そんなものよ
というような、軽い使い方をすることもあります。
「可哀想」とか「同情する」という表現よりも、もしかしたら軽く使いやすい言葉になっているのではないでしょうか。
その点に関しては、時代の流れによって言葉の使い方が変わることがあるので仕方ないのかも知れませんね。
「気の毒」の語源
「気の毒」の語源を調べてみると「気の薬」に対義する言葉として生まれたという説を見つけました。
「気の薬」とは、心の保養になること、気を晴らすことになること、心のなぐさめになることを指す言葉です。
現代の言葉に言い換えると、「癒される」でしょうか。
リラックス、充電、心の栄養など、色々な表現があります。
「気の薬」とは、幸せを感じたり、楽しくなるようなことを示す言葉なわけです。
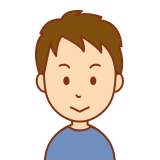
美しい風景は気の薬になるな
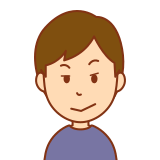
久しぶりに体を動かしたから気分がイイよ!
スポーツは気の薬にもなるね
今はほとんど使われませんが、「気の薬」を今の時代にも使うとなれば、このような会話で聞かれるのでしょうね。
その対義語として生まれたのが「気の毒」だったので、本来は自分以外の人に対して同情したり、可哀想に思うことではなく、自分自身の心に害を及ぼすことを表す言葉だったのでしょう。
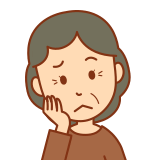
ご近所の井戸端会議で
噂話ばかり聞かされるのは
気の毒にしかならないわ
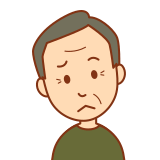
このごろ夜中の騒音がひどいな
気になって気の毒だ
「気の薬」に対して生まれたのであれば、ほんとうはこのような使い方をしていたはずなのです。
いつの間にか、変わってしまったのでしょう。
まとめ
「気の毒」の意味や語源について調べてみると、今は聞くこともなくなった「気の薬」という言葉があり、それに対して生まれたのだとわかりました。
「気の薬」だけはほとんど消えてしまったなんて、気の毒な話ですね。