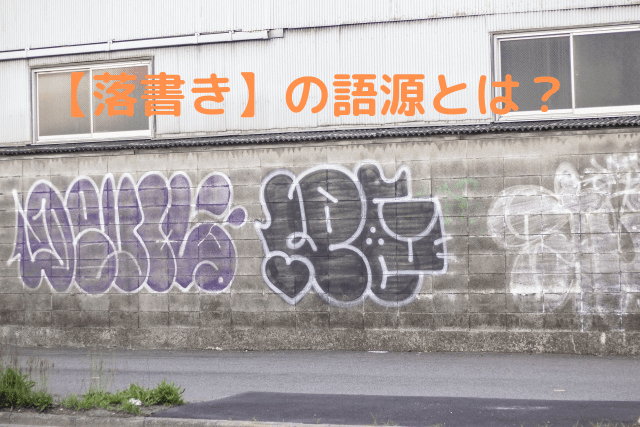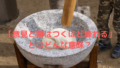落書きと言えば、いたずら書きのようなものから、ちょっと芸術性を感じるようなアートな落書きまで色々あります。
子供が好きなものを書くための「らくがき帳」なんていうのもありますよね。
さて、この「落書き」という言葉ですが、語源は何なのでしょう。
当たり前に使っていますが、語源については考えてみたこともありませんでした。
どんなことが由来になったのか、調べてみました。
「落書き」の意味
「落書き」とは、
本来は本来は書いてはいけない場所にいたずら書きをすること。
また、そのいたずら書きのこと。
という意味です。
つまり、書いた文字や絵などの質には関係なく、書いてはいけないところに書いたものを全て「落書き」と呼ぶわけですね。
そう考えると、幼い子供たちが好きなものを書くための「らくがき帳」は、ちょっと違うような気がしますよね。
書いてはいけないところに書くのが落書きのはず。

はい、らくがき帳をあげるよ。
ここに何でも好きなように書きなさい。

やったー!らくがき帳だ!
どうもおかしな感じです。
ですが、よく考えればわかりました。
書いてはいけない場所にいたずら書きされないために、好きなものを自由に書くための「らくがき帳」が存在するのでしょう。
「落書き」の語源
書いてはいけないところに書くいたずら書きを「落書き」というようになった語源をさかのぼってみると、平安時代の初期までさかのぼります。
権力者や社会に対する不満を持っている人は、いつも時代にもいます。
平安時代は、身分の差が今よりもハッキリしていたので、極端な格差社会でしたから、い現代よりもずっと不満を抱えて生きている人が多かったのではないでしょうか。
今のように、SNSを使って社会や権力への批判をすることができなかった時代ですが、何とかして世の中への不満を訴えかける方法を工夫したのだと思います。
それが「落書き」の語源になっら落書(らくしょ)です。
落書とは、時の権力者や政治に対する批判や風刺画を人名を伏せて書き、人々の目につくところに貼り出したり、バラまいたりする文書のことです。
権力者の評判を落とす目的が落書の語源という説と、文書を落として人々の目に触れさせるから落書という説があります。
それがいつしか「らくがき」と読まれるようになり、現在に至るわけです。
落書きアートのついて
世界に名を知られるバンクシーというアーティストがいます。
匿名で活動しているので、どんな人物なのかわかりません。
バンクシーは路上芸術家と呼ばれていて、権力や社会を批判するかのようなメッセージ性を感じさせる作品を残しています。
そういう意味では、落書きの語源になった落書に通じますね。
有名になったので、本来は許可されていないであろう場所に残る作品も、消されずに残されているところもあります。
彼ほど有名になれば、落書きでも価値のある作品として扱われるようになりますが、下手に真似すると罪に問われるのでやめましょう。
まとめ
「落書き」の語源が権力や社会への批判や風刺が由来だったとは、あまり知られていないのではないでしょうか。
街中で見かけるスプレーを使った落書きには、そんな深い意味はないと思いますが、社会への不満も少しは影響しているのかも知れませんね。
いずれにしても、どんなにすばらしいアート作品でも、書いてはいけない場所に書くのは犯罪なので、絶対にしてはいけないことだけは間違いありません。