年末になるとあちこちで耳にするのが「よいお年を~」というフレーズです。
この言葉を聞くと、いよいよ今年も終わりなのだな・・と感じます。
でも、この「よいお年を~」はいつから使うのか迷いませんか?
12月の何日以降に使うというルールでもあるのか、疑問に思ったことはないでしょうか。
「よいお年を~」を使い始めるタイミングや、いつまで使えるのかなど、年末の挨拶に関する疑問を解説します。
「よいお年を~」とは
「よいお年を~」と言うことが多いですが、正しくは「よいお年をお迎えください」を略したものです。
年を迎えるとは、新年を迎えるというそのままの意味でもありますが、年神様という元旦にその家にいらっしゃる神様を迎える意味でもあります。

門松やしめ縄を飾り、鏡餅をお供えするのは年神様を迎える準備です。
その一年を無事に過ごせるように守ってくださる神様として年神様を迎えるのが日本のお正月の風習です。
「よいお年をお迎えください」とは、穏やかに新年(年神様)を迎えてくださいという願いを込めている年末だけの特別な挨拶なのですね。
「よいお年を~」はいつから使える
「よいお年をお迎えください」という挨拶は、12月の中旬くらいから使います。
もしも11月下旬や12月初旬に会った人に対して使うのは、マナー違反ではなくても違和感を与えてしまう可能性があります。
絶対にこの人とは今年中には会うことはない!と断言できるとしても早すぎるのはちょっと失礼な感じです。
目安としては12月中旬以降です。
ただ、さほど顔を会わせる機会のない人に12月の初旬に会った場合などは、迷います。
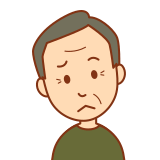
たぶん、次に会うのは随分先のことになるだろう・・
そう思っているのなら、年末の挨拶をしたくなりますよね。
そういう場合場合は、「少し早いですけど、よいお年をお迎えくださいね」と付け加えるようにしましょう。
ですが12月は師走というように、誰でもバタバタと忙しくしている時期です。
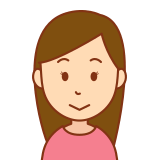
年の瀬は忙しいのでお体にはお気を付けください
というような、相手を気遣う挨拶でも良いでしょう。
年末を感じさせる挨拶は色々あるので、年内に会うのが最後だからと思っても、焦って「よいお年を~」を使わなくてもよいのではないでしょうか。
「よいお年を~」はいつまで使える?

「よいお年をお迎えください」は12月30日まで使えます。
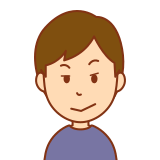
え??12月31日には使わないの?
と思いますよね。
大晦日にもあちらこちらで聞くのに・・と不思議に思うのですが、よく考えると理由がわかります。
年末に新年の準備をするのは12月30日までに終わらせるものです。
大晦日は新年を迎える準備を全て終えているから、12月31日には「よいお年をお迎えください」よりも「来年もどうぞよろしくお願いします」という挨拶の方が適しているのです。
ですが、12月31日ギリギリまで仕事している人も多いのが今の世の中です。
大晦日までに新年の準備ができない人だっていると思います。
そのような場合は「よいお年を~、来年もよろしくお願いします」と合わせた挨拶にすると良いではないでしょうか。
まとめ
「よいお年をお迎えください」という挨拶は、誰に急かされているわけでもないのに気持ちばかりが焦る時にほっと一息つける魔法の挨拶のような感じがします。
期間限定なのでなおさらですね。
美しい挨拶だな・・って思うので、大切に使いたいと思います。


