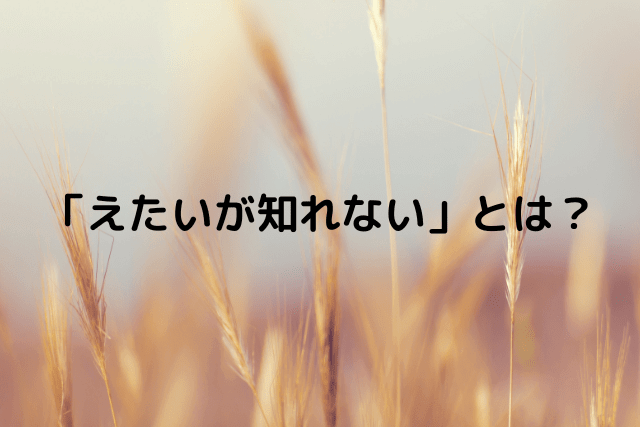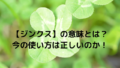「えたいが知れない」というのは、どんなことをあらわすのかわかりますか?
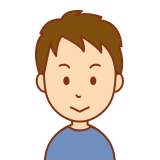
正体がわからないものでは?
ほとんどの人はそのように理解して、「えたいが知れない」という言葉を使っていると思います。
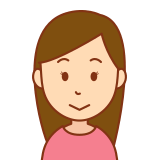
それで正解でしょ?
意味はそれで間違いはないとしても、なぜ正体がわからないものに対して「えたいが知れない」というのでしょうね。
この言葉の本来の意味や語源について、調べてみましょう。
「えたいが知れない」とは
「えたいが知れない」のえたいは漢字では得体と書きます。
この字が使われた意味を探ると、語源にたどり着くのかも知れませんが、その前に得体の意味を調べてみました。
出自、素性を含めたものの正体
新明解国語辞典
このように書かれていました。
出自とは、出どころや生まれのことです。
素性とは生まれ、育ち、血筋、家柄という意味です。
つまり、その人物の素性がわからないことをあらわす言葉が「得体が知れない」なのです。
「えたいが知れない」の語源
「えたいが知れない」の得体の語源は、2つの説が有力だとして伝わっています。
それぞれに言葉の意味につながる説なので、どちらも語源に相応しい気がしますが、ハッキリとは確定されていません。
それぞれの語源の説を見てみましょう。
為体(ていたらく)から転じた
得体は為体(ていたらく)が転じた言葉だという説があります。
為体の音読みは「いたい」または「えてい」です。
為体は、人に対して叱るときに使う言葉になっていますが、そもそもの意味は物事の様子や状態を示す言葉でした。
つまり、得体が知れないとは、為体が不明ということから転じて生まれた言葉ではないかと言われているわけです。
僧侶の衣
得体の語源としてもうひとつ有力だと言われているのが、僧侶の衣です。
得体はもともと衣体と書いていたのが変化して、得体になったという説です。
なぜ得体が知れないという意味の得体の語源が僧侶の衣なのか・・。
これは衣によって宗派や僧の格式が判別できたからです。
しかし、お坊さんが身につけている衣を見ても、宗派や格式がよくわからないこともありました。
それは宗派を破門されたり、修行の途中で逃げ出したような人もいるからです。
そういうお坊さんを見ると、人々は「どこから来たのかわからない」と思ったのではないでしょうか。
そこから、衣体からでは素性がわからなということで「えたいが知れない」というようになったと伝わる説です。
まとめ
「得体」の語源が為体なのか衣体なのか、それはハッキリわかっていません。
ただ、お坊さんの衣が語源というのは、俗説のようなイメージがあるため、一般的には為体の音読みが転じて、そこから「得体が知れない」という言葉になったという説が有力です。