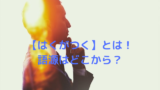結婚披露宴で新郎新婦の職場の上司などがスピーチをした後に、「これをもって、私の挨拶と代えさせていただきます。」などと締めくくることがあります。
今まで長々と話していたのは、何だったのか?と思わず突っ込みたくなることがあります。
挨拶とは、「おはよう」「こんにちは」「こんばんは」のようなものから、「はじめまして」や「よろしくおねがいします」など、相手や場所によって使い分けます。
披露宴のスピーチなどでは、新郎新婦との関係性など、出席者にわかるように簡単に自己紹介をしますし、親族へのお祝いの言葉なども入るはずです。
挨拶として、十分すぎるほどの時間をかけているはずです。
「これにて挨拶と代えさせていただきます」という締めくくる意味が、よく理解できないのです。
「挨拶に代える」とは、どんな意味があるのか調べてみましょう。
「挨拶に代える」の意味
「挨拶に代える」とは、他の方法で挨拶に代えるという意味です。
冒頭にも例えとして出しましたが、結婚披露宴のスピーチの締めくくりの言葉に使います。
他にも、学校行事や自治体のイベントの開閉式の言葉の締めくくりなどにも使います。
お礼状など、書面で挨拶する時などにも「書面にて挨拶と代えさせていただきます」など。
スピーチや書面などで、挨拶の代わりにするという意味で「挨拶に代える」と使うのが一般的です。
結婚披露宴などでは、出席者に個別に挨拶することはできないので、前に立ってスピーチすることで、個別への挨拶の代わりにするという意味も含まれると考えます。
「挨拶に代える」の由来
「挨拶に代える」という言葉は、謙遜の気持ちから生まれたと考えられています。
それは、このような気持ちから生まれたと言われています。
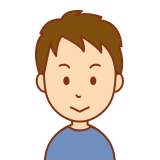
私のようなつまらない人間の話などは、挨拶と呼べるような立派なものではありませんが、挨拶として代用させてください。
謙遜し過ぎのような印象ですが、日本人らしいと言えばらしいですよね。
長々と話をしていたのに、終わる頃になって、急に我に返って「挨拶に代える」のも変ですが、日本人は謙遜することが美徳と考えられるため、挨拶の締めくくりの言葉として付けるのが礼儀のようになっているのです。
挨拶以外に代える言葉
スピーチの終わりに「挨拶に代えさせていただきます」と締めくくるのは、人前で話す時の礼儀として定着しています。
しかし、掘り下げてしまうと、スピーチは雑談のことなので、堅苦しい挨拶とは別と考えた方が良いのです。
ですが、人前で話すことに慣れていない人がスピーチする時の締めの言葉としては、とても使いやすく、無難なので便利に使われるのではないでしょうか。
じつは結婚披露宴のスピーチでは、「挨拶に代える」よりも「お祝いの言葉に代える」と言い換えることもあります。
また、「お礼の言葉に代える」と言い換えることもあります。
お祝いの言葉も、お礼の言葉も、大きな括りでは挨拶に含まれますが、その場に応じて言い換えるようになっています。
まとめ
「挨拶に代える」という言葉には、謙遜の気持ちが込められていました。
「簡単ではありますが、挨拶に代えさせていただきます」になると、さらに謙遜の気持ちを強調しています。
つくづく、謙遜するのが好きなんだな・・と思ってしまいました。